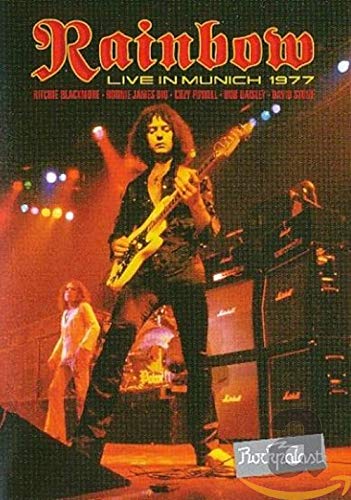Night of the Hawks / HAWKWIND (1984/2001)
1984年にJettisoundz VideoからリリースされたHAWKWINDのライブビデオで、同1984年3月イプスウィッチのGaumont Theatreでのステージの模様を収録している。再生時間は55分程度。
おそらくHAWKWINDのライブ映像のなかで最もはやく販売されたもので、翌1985年には日本でも『幽星空間』の邦題でリリースされた。国内版はVHSのほかにベータもあったらしい。
メンバー
- デイヴ・ブロック Dave Brock:Guitar, Keyboards, Vocals
- ヒュー・ロイド・ラントン Huw Lloyd-Langton:Lead Guitar, Vocals
- ハーヴィー・ベインブリッジ Harvey Bainbridge:Bass, Vocals
- ニック・ターナー Nik Turner:Vocals, Saxophone
- デッド・フレッド Dead Fred Reeves:Keyboards, Violin
- クライヴ・ディーマー Clive Deamer:Drums
このメンバーでぱっと目につくのはやはりニック・ターナーの復帰だろう。彼はこの時期スティーヴ・トゥックのバンドのメンバーと組んだINNER CITY UNITというポスト・パンク的なグループでも活動しており、デッド・フレッドはそのICUのキーボーディスト。
HAWKWIND側は1982年の『Choose Your Masques』から1985年の『The Chronicle of the Black Sword』に至るまでの、RCAとの契約が切れロバート・カルバートとのプロジェクトが頓挫しという、FlicknifeからシングルやEPそしてコンピの類がごちゃっとリリースされてはいたものの「新作スタジオアルバム」が途切れていた時期にあたる。
結局ニック・ターナーが正式に参加したアルバムは作られずに終わったがライブ活動は精力的に行っていて、さらにライブビデオもニックが参加している期間のものだけで2本リリースしている(片方はHAWKWIND単独のビデオじゃないけど)。
内容
本作『Night of the Hawks』は上記の2本のうち先にリリースされたもので、おそらくHAWKWINDとしての最初のビデオリリースにあたるんじゃないかと思う。
タイトルは同時期にシングルおよびEPでリリースされた新曲「Night of the Hawks」と共通で、パッケージのイラストもトリミングされてはいるがそのEPと共通のもの。
このビデオ含め“Earth Ritual”と銘打たれた1984年ツアーに連動した企画だったと思われる。
HAWKWINDは70年代からアルバムにダンサーや照明スタッフの名前も記載するなどライブでの演出に独自のこだわりがあるグループで、このEarth Ritualツアーでもたくさんの照明と大掛かりな舞台セットを使用して派手にステージを演出していたはずなんだけど、ぶっちゃけ本作を観てもそういうのはよくわからんです。
というのもこの映像は一部のメンバーを中心に捉えたショットが大半を占めていて、ニック・ターナーを中心にヒュー・ロイド・ラントンやデイヴ・ブロックはある程度なにをやってるかわかるもののデッド・フレッドはたまに3人の奥に映る程度、クライヴ・ディーマーにいたってはほとんど映らない。
そしてステージ全景を捉えるようなショットが皆無なので、なんならステージの規模や舞台セットがさっぱり把握できないのである。
たぶんだけど、照明に気合が入っているがゆえにステージが基本的に暗くてしかも明るい瞬間との差が大きく、それを当時の機材(おそらくテレビ局が使ってるようなものより低予算の)で撮影しているもんだからちょっと引いたショットを撮ろうとするとすぐ光量不足になる一方でメンバーに寄ると今度は照明がついた瞬間に明るくなりすぎ、さらにストロボまでばりばり使ってるという条件のなかでどうにかバランスをとった結果がこの限られた画角と全体的に荒い画質なんじゃないかと思う。
そうした問題に比べればいかにも昔のテレビ向けライブ映像らしいよくわからない画像エフェクトやレーザーグラフィックス、一瞬再生側の問題かとドキッとするコマ落としみたいな演出なんて愛嬌みたいなもんです。
まあ欠点の多い映像ではあるが、演奏自体はブロックの荒いサウンドと終始黙々と弾きまくるラントンが特徴のハードロックに接近した感のある80年代のパフォーマンスを楽しめるし、プレイより存在そのものの方がインパクトあるニックだけでなくこのあとキーボードに転向するベインブリッジがベースを弾く姿やデッド・フレッドがヴァイオリンを弾く様子もちらっと確認できる。
こうして聴くとクライヴ・ディーマーのドラムはそれなりに派手さを出しつつもスマートに決めていてとても良く、一時的な参加で終わってしまったのはもったいなかった。ただこのひとってこの後PORTISHEADのレコーディングに参加したりロバート・プラントやRADIOHEADのツアーメンバーになったりするので、むしろこういうバンドのレギュラー・メンバーになってもらえるような人材ではなかったかもしれないけど。
とにかくこの時期のHAWKWINDのライブの模様を垣間見られるだけでありがたいリリースなんだけど、逆に言えばそこで喜べてかつこのバンド特有のおおらかさ(当たり障りのない表現)を愛でられる一部の好き者以外にはまったく薦められるものではないのでご注意ください。
んでこの真ん中のあきらかにひとりだけ格好がおかしいのはどちらさま? えっこれがニック?
以前ネットのどこか(この記事書くにあたってあれこれ検索してみたんだけど見つけられず)で紹介されていたこの時期のライブレポートではニックのステージ上での振る舞いやコスチュームについて批判的で、「しまいには裸にゴミ袋をまとっただけの姿になっていた」みたいな書かれ方をしていた。
そのときは「いやいやさすがにそんな笑」とスルー気味だったものの、本作の終盤ではマジでそういう格好になってるのが確認できる。なぜズボンを脱いでしまったのか。
ニックはヴォーカルとサックスを担当しつつあの格好でステージ上をのそのそと動き回っていて、ICUの曲である「Watching the Grass Grow」(ブロックのギターがやたら荒いもんだから本家以上にハードコア系のパンクっぽくなってる)とか自身が関わってる70年代の曲ではまだしも上に貼った「PSI Power」みたいな無関係の曲だとちょっと手持ち無沙汰っぽい。
そもそもニック作の「Brainstorm」ではひさしぶりに作曲者本人によるリードヴォーカルが聴けるんだけど、なんか以前より歌いまわしがやたらねちっこくなってて、BLUE ÖYSTER CULTの「Astronomy」が年代を経るごとにライブでの歌いまわしが変になっていったのを思い起こさせる(突然引き合いに出す)。
あと『Live Seventy Nine』で葬り去られた(再録版?なんですかそれ?)はずが以降もライブではふつうに演奏してる大ヒット曲「Silver Machine」ではなんか客をステージにあげてダンスコンテストをやってる。フランク・ザッパもやってたなぁこういうの……
DVD
本作は2001年にCherry Red傘下のVisionary Communications Ltd.からDVDリイシューされた。HAWKWINDのDVDはPALが多くて難儀するが本作ふくめCherry Red関連のリリースはNTSCのリージョンフリーでひと安心。
オリジナルのVHSはおそらくモノラル音声で、このDVDではバンドの演奏はモノラルっぽい音像だけどなんとなく広がりがあり、歓声とか電子音は左右にくっきり分かれたりもする。
パッケージの裏面には「If your system includes 5.1 audio, you should be able to switch the amplifier to activate simulated 5.1 SURROUND SOUND, to enhance this archive recording.」という表記があるので、いちおうマトリクス方式でエンコードされたサラウンド音声ではあるのだと思われる。
ドルビープロロジックIIを通して再生してみるとなんとなくぼやけてたバンド演奏の定位がよくなり、多少奥行き感がでたり歓声が後ろにまわったりするので、まあ使える環境なら使っておいてもいいかなくらい。
たぶんリミックスとかではなく元になった音声ソースを擬似的に加工してるんじゃないかと。
昔のバンドのDVDって商品価値を高めるためかよく擬似的に作れられたとおぼしき無意味どころか耳障りだったりする5.1chサラウンドの音声が収録されているけど、これはまあふつうに聴けるステレオ音声にプロロジック通すとちょっといい感じになるという程度のものでしかないので逆に良心的なんじゃないかと。
DVDにはオマケで「Night of the Hawks」のPVが収録されている。当時のライブ映像にスタジオ版の音声をあてたもので、レミーのゲスト参加が話題になった曲だけど映像ではふつうにベインブリッジがベースを弾いてる。
2006年にCherry Redからこの『Night of the Hawks』に加えて『The Chronicle of the Black Sword』と『Love in Space』という3つの映像作品をまとめた3枚組廉価セットがリリースされた。
それぞれのディスクは単品リリースとまったくおなじもので、当時はバラで買うよりずっと安かったので自分はこれを購入しました。まあそもそもつべに本編動画がまるまるアップされてるとかされてないとか
Warrior on the Edge of Time / HAWKWIND (1975/2013)

1975年5月にリリースされたHAWKWINDの5thアルバム。
UKアルバム・チャートで13位を記録し、最高傑作に挙げるファンも多い彼らの代表作のひとつ。当時国内盤もリリースされ、邦題は『絶体絶命』だった。
- デイヴ・ブロック Dave Brock:Guitar, Synthesiser, Bass Guitar (A4), Vocal (A1, A2, A5, B1, B6)
- ニック・ターナー Nik Turner:Tenor and Soprano Sax, Flute, Vocal (B2, B5)
- レミー Lemmy:Bass Guitar
- サイモン・ハウス Simon House:Mellotron, Moog, Piano, Synthesiser and Violin
- サイモン・キング Simon King:Drums and Percussion
- アラン・パウエル Allan Powell:Drums and Percussion
- マイケル・ムアコック Mike Moorcock:Vocal (A3, B4)
前作から引き続きサイモン・ハウスがヴァイオリン、メロトロン、シンセサイザーを担当。デル・デットマーが脱退した一方でサイモン・キングの怪我の療養中に代理でツアーに参加したアラン・パウエルはそのまま残り、ツイン・ドラム体制となった。
バンドはまず1975年1月にOlympic Studiosで3曲をレコーディングし、うち2曲「Kings of Speed」と「Motorhead」がシングルとして3月にリリースされる(残る1曲は「Spiral Galaxy 28948」)。
他のトラックは3月にRockfield Studiosでレコーディング、その後Olympic Studiosでミキシング作業が行われた。
プロデュースは例によってHAWKWIND名義となっていて、われらがデイヴ・ブロック船長が采配を振るっていたと思われる。
ちなみに3月のあいだに急ピッチでミキシングまで済ませたのは4月からはじまるUSツアーにあわせ新作が必要になったかららしいのだが、そのUSツアーにおいてあのレミー解雇事件が起こる。
レミーはUSツアー中カナダ入国の際にコカイン所持の疑い(実際にはアンフェタミンだった)により拘留され、結局バンド側は彼を解雇しPINK FAIRIESのメンバーでカナダ人のポール・ルドルフを代役としてツアーを続けることになった。
この件が原因でせっかくのツアーが中止される心配があったのに加えて、ここに至るまでに燻ってたいわゆる人間関係的なやつとかそもそもバンド内で彼のドラッグ癖が問題視されていたことも響いたようだ。
HAWKWINDはメンバー全員薬漬けみたいなイメージがあるし実際そういう面もあっただろうけど、同時にリーダーのデイヴ・ブロックはわりと「クリーン」だったらしく、レミーに限らずドラッグの濫用が目に余るメンバーは解雇されることもあったりする。あと近年はそもそも平均年齢が高くなって残っているのは健康志向のメンバーばっかりみたい。
さてさて、今作はイギリスの小説家マイケル・ムアコックの『エターナル・チャンピオン』シリーズを題材としていて、明確なストーリーこそ無いもののアルバムを通してそこはかとなくそれっぽい流れを形成している。
ムアコックはこれ以前からHAWKWINDのメンバーと交流があり、今作ではコンセプト段階から協力し詩を提供するとともに、自身も朗読で参加。あとバックコーラスも歌ったけど結局使われなかったりタダ働き状態だったりとインタビューでちょくちょく愚痴っている。
アルバムのアートワークもコンセプトに沿ったものになっていて、本国イギリスでの初期盤はゲートフォールドのジャケットをさらに展開すると裏面がムアコックの小説に登場する「CHAOS」の文字をあしらった盾になるという凝った作りになっていた。
アート・ディレクションにはComte Pierre D'AuvergneとEddie Brashというふたりの名前がクレジットされているがどちらも偽名。
Eddie Brashはバーニー・バブルスのことだそうなので、おそらく両面ともイラストは彼の手によるものなのだろう。
Comte Pierre D'Auvergneというなかなかに偽名らしい偽名を使っているのはソングライターやレコードプロデューサーとして有名なUnited Artists Recordsのピエール・タブスで、この展開するレコードジャケットは彼のアイディアによるものらしい。


いい感じに撮影できるような代物じゃないだろこれ……
表側のイラストは断崖絶壁に佇む騎士らしきシルエットと中央に太陽をあしらった風景だが、ジャケットを展開すると反対側にも鏡写しのように同じ風景が現れ、全体が太陽の部分を目とした「兜をかぶった人間の顔」のように、あるいはホモ・サピエンスのオスの生殖器のうちの体外に露出している部分のように見える構図になっている。
このジャケットのギミック、はじめて見たときからずっと「いやこれどう見てもちんちんでしょ」と思ってたんだけどなぜか同じことを言ってるひとが周囲にもネットにも全然いなくて、後述するAtomhengeリイシューのブックレットに「ジャケットを広げるとでっかいペニスになるんだよ!」というメンバーの発言が引用されているのを見つけるまでずっとこれを男根だと思ってるの俺だけだったりするんじゃねーかという不安に苛まれ昼しか寝られない日々を過ごしておりました。いや昼間はいくらでも寝られるのに夜となると昼の間どれだけ活動的でもなかなかぐっすりとは寝られない体質なのは子供の頃から変わらないんですが
A1「Assault and Battery - Part One」
A2「The Golden Void - Part Two」
メドレーではあるが実質ふたつあわせて1曲で、近年のリイシューでは最初から「Assault and Battery / The Golden Void」とひとつのトラックにまとめられている。
冒頭から力強いベースのもとメロトロンがぶわーっと湧き上がり、ドラムはさっそくツインであることを印象づけるようなコンビネーションを披露し、フルートはなんかうにゃうにゃ言い、ヴォーカルが入ってくるころにはもう名曲確定みたいな楽曲。
しかもそこで「じゃあ後はいつもどおりな感じで」とはならず、中盤にはずいぶんドラマティックな展開がぶち込まれる。
ちょっとどうしちゃったのってくらいの充実ぶりだけど、基本的には前作『Hall of the Mountain Grill』で急に増えたやたら叙情的な曲調をうまいこともともとHAWKWINDが得意なタイプの演奏フォーマットに乗っけた感じもある。でも結局こういうのは後にも先にもこれ1曲だけでした。
ちなみに歌詞の一部はヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの「人生讃歌 (A Psalm of Life)」そのまんま。
A3「The Wizard Blew His Horn」
ムアコックの詩による朗読曲その1。
A4「Opa-Loka」
あまりにもNEU!。ちなみにデイヴ・ブロックはNEU!の1stアルバムUK盤にスリーブノートを寄稿してたりする。
ただし楽曲のクレジットはキングとパウエルであり、ドラム勢がこういうのやりたいってなった面もあるのだと思われる。とはいってもHAWKWINDの場合最終的にそれを採用するか決めるのにブロックの意思が影響を及ぼしていないわけがないのであるが。
このアルバムでのキングとパウエルのドラムは、「Assault and Battery」と「Magnu」のイントロこそツインドラムであることを強調するような感じではあるものの、全体としてはキングひとりのときよりタイトでシンプルなプレイスタイルが中心になっている。
そうすることで一体感を高めているのと同時に、片方がドラムセットに専念してるあいだにもう一方はパーカッション類を扱うという方向にもツインドラムが活かされてる印象で、このトラックもツインドラムでアパッチビートを行うことで左右のチャンネル間をぐるぐる回るような効果を出すと同時に片方がマラカス(たぶん)を加えてそれを補強したりしている。
あとこのトラックだけブロックがベースを弾いてる。レミーは居眠りしてたらしい。
ロバート・カルバートの復帰後にライブでも採り上げられたが、その際にはカルバートによる「Vikings On Mars」という歌詞がつけられており、これが「Uncle Sam's On Mars」に発展したという。
A5「The Demented Man」
ブロックの諸行無常系弾き語り曲だが、メロトロンとシンセの伴奏でいい感じにヒロイックファンタジーっぽい壮大かつどこか悲劇的な雰囲気を盛り上げている。
個人的にうれしいのは、今作が全体的にメロトロンぶわーで雰囲気作りをやりつつも、前作ほどには叙情の沼にどっぷりとハマらずそれなりの距離感を保っていること。
初期のレーベル面では「The Demented King」と表記されていた。
B1「Magnu」
B面冒頭を飾る「Assault and Battery / The Golden Void」と並んでこのアルバムを象徴する楽曲で、こちらはより単純明快な、この面子でスタジオ入りしてせーので演奏したらこうなりました的な仕上がり。
オープニングの強烈なツインドラムにはじまり全編にわたってハウスのヴァイオリンがアラビア風にのたうち、電子音が飛び交い、やる気あるんだかなんだかわからんサックスがぶいぶい吹いてまわり、しまいにはギターもうねりだしてえらいこっちゃ。
逆に前作までだったらど真ん中に陣取っていただろうレミーの影が薄いのだけど、そもそも「まともなリード奏者の不在」という状況がレミーをバンドのフロントマンに押し上げていたと考えると、サイモン・ハウスの登場でその状況が崩れたという面もあるんじゃないかと思わないでもない。
歌詞はイギリスで1896年に出版された『Fairy Tales of the Slav Peasants and Herdsmen』というスラブのお伽噺を翻訳した書籍のなかの一編が下敷きになっていて、さらにパーシー・シェリーの「アポロの讃歌 (Hymn of Apollo)」の丸パk、もとい引用も含まれる。
B2「Standing at the Edge」
ムアコックの詩による朗読曲その2で、これだけニックが朗読を担当。青牡蠣教信者としては"Veterans of a Thousand Psychic Wars"というフレーズにぴくっと反応してしまう。
B3「Spiral Galaxy 28948」
ハウス作のインストで、シンセの多重録音とバンド演奏を組み合わせたなかなか意欲的なトラック。このアルバムでのハウスはほんと八面六臂の活躍ぶり。
たぶん「The Golden Void」で耳をつんざくような高音を出してるのと同じシンセ(miniKorgだろうか)でリードをとっている。
タイトルの「28948」はハウスの誕生日の数字を並べただけで特に意味はないらしい。
B4「Warriors」
ムアコックの詩による朗読曲その3。
B5「Dying Seas」
ニック作。朗読曲のあとの盛り上げどころなわりにあっさり気味で、しかも次の曲が次の曲なので繋ぎとして機能していない。このあたり制作時間が短くて煮詰める時間が足りなかったんじゃないだろうか。
B6「Kings of Speed」
マイケル・ムアコックが自分のアルバムのために用意していた歌詞にブロックが曲をつけたもので、ムアコックの『ジェリー・コーネリアス』 シリーズがモチーフになっている。
えっ締めはこういう曲調でいくんですか!?と思わんでもない唐突さだけど、あらためて聴いてみるといちばん次作での変化を予感させる楽曲でもあるかもしれない。
米Atco盤では英盤のアルバム・バージョンから多少間奏がカットされたシングル・バージョンが収録されているらしい(未聴)。
このアルバム、ファンからの評価が高いし個人的にも大好きで思い入れがあるけど、よく言われるような完成度の高い作品というよりはむしろAB両面の冒頭曲の雰囲気作りが完璧なあまり聴いてる側が勝手に「その気」になりがちな中身の凸凹した作品、といったほうがふさわしいような気もする。
2013 Atomhenge Reissue:Super Deluxe Boxset Limited Edition
今作はイギリスでは前作までとおなじくUnited Artistsから、アメリカではAtcoからリリースされた。当時日本では東芝EMIから国内盤がリリースされたほか、1981年にはキングレコードの「ユーロピアン・ロック・コレクション」の1枚として再発されている。自分がはじめて聴いたのは親戚のひとのレコードラックにあったこの再発盤でした。
90年代前半にはDojoやGriffinといったレーベルから盤起こしや米盤用マスターのコピーからCD化されたりはしたものの、EMIによるUnited Artists時代の一連のアルバムをリマスターしたシリーズには含まれず、それ以降も公式なリイシューが行われないまま放置状態になってしまっていた。
一時期はあまりの再発されなさにマスターテープ紛失との噂がまことしやかに語られたりもしたものの、実際には権利関係の問題が解決できなかったことが原因らしい。
なんでもHAWKWINDは今作から自分たちで版権を管理するようになったらしいのだがそれが災いし再発の手続きが複雑になってしまい、加えて自身も権利の一部を保有する当時のマネージャーであるダグ・スミスが再発を目指して交渉をすすめたものの彼とレミーの不仲が大きく影響した模様。
ダグ・スミスはかつてMOTÖRHEADのマネージャーも務めていたが後に多額の用途不明金をめぐってレミーと裁判になっており、結局示談になったものの以降レミーはダグ絡みの話はすべて拒絶していたという。
2013年にようやくCherry Red傘下のHAWKWIND専門レーベルであるAtomhengeからリイシューされたが、この際には自身もバンドの熱心なファンらしいマーク・パウエルが交渉を進め、レミー分の権利はデイヴ・ブロックが買い上げてCherry Redと契約する形をとったという。
以前は今作に限らずRock Fever Music等の非公式盤が横行し全体的に質の低いCDがごろごろしていたHAWKWINDであるが、権利関係のきちんとしたAtomhengeの登場とその丁寧なリイシューによって状況は一気に改善されました。ありがてえありがてえ
収録内容
この2013年AtomhengeリイシューはStandard Edition、Three Disc Expanded Edition、Super Deluxe Boxset Limited Editionの3つの仕様が用意された。
Standard EditionはシンプルなCD1枚、Three Disc Expanded EditionはCD2枚とDVD、Super Deluxe Boxset Limited EditionはCD2枚とDVDに加えてLPとポスターとか諸々のオマケがついている。
今回取り扱うSuper Deluxe Boxset Limited Editionに収録されているのは以下の音源。
- CD1:新規リマスター音源+8曲のボーナストラック(うち5つはこれまで未発表)
- CD2:Steven Wilsonによるマルチトラック・マスターからのステレオ・リミックス音源+5曲のボーナストラック(うち2つが未発表)
- DVD:Steven Wilsonによるステレオ及び5.1chサラウンド・リミックス音源+オリジナル・ステレオ・マスターからの24bit/96kHzフラット・トランスファー音源
- LP:オリジナル(カッティング)マスターからカットされた180g重量盤
リマスター
マスタリング・エンジニアはThe Audio Archiving CompanyのBen Wiseman。UniversalやEsoteric Recordingsで多くのアルバムを手掛ける人物であり、Atomhengeにおけるリマスターのほぼすべてを担当している。
The Audio Archiving Companyのリマスターにはマスター・テープ由来のノイズを除去しつつオリジナルのバランスを壊さない範囲でクリアかつ現代的な方向へ調整を行う、という一貫した方針があるように感じる。
今作のリマスタリングもその方針に沿った、安定した仕上がりとなっている。
DR値と「Assault & Battery / The Golden Void」の波形。前のブログでこのリイシュー扱ったときはずいぶん気合入れてたみたいでこんな画像まで用意してたので、せっかくだし貼っとく。
見ての通り、CDの器からはみ出さない(=潰さない)範囲で音圧や各曲の音量バランスが整えられている。
ステレオ・リミックス
Steven Wilsonは自身もPORCUPINE TREEやソロを中心に活動するミュージシャンであり、KING CRIMSONやXTC等のサラウンド及びステレオ・リミックスでも高い評価を得ている。
奇をてらったり現代的な音作りを意識し過ぎたりするようなことのないオリジナルのバランスを大切にしつつ再構成した仕上がりに定評があり、このステレオ・リミックスもその評価に違わぬもの。
各楽器やその残響が高音域までなめらかに伸びる一方でオリジナルではその高音がキツめだった「Assault & Battery」「Spiral Galaxy 28948」のシンセや「Magnu」間奏部分でヴァイオリン、サックス、ギター、シンセが折り重なり混沌となる場面が整えられ、格段に鳴らしやすくなった。
このボックス収録の音源のなかでもっとも余計なことに気を取られず素直に没頭できるのがこのステレオ・リミックスだと思う。
おなじくDR値と「Assault & Battery / The Golden Void」の波形。
リマスターよりほんの少しだけDR値が大きいが全体としては大差ない程度で、「Assault & Battery / The Golden Void」のみピークが0.00dBに達している。
5.1chサラウンド・リミックス
ステレオ・リミックスと同じくSteven Wilsonが担当。
聞くところによると今作はもともとのマルチ・トラックのトラック割り等が独特で、リミックスにあたっての制約が多かったようだ。
実際「Assault & Battery」や「Magnu」といった目玉となる長尺曲では思ったほど音を動かしておらず、メロトロンや各楽器の残響をうまくつかってリスナーを包み込むようなフィールドを形成することに重点を置いている印象。
その一方で3つの朗読曲や「Spiral Galaxy 28948」ではもっと積極的に音を動かして目くるめく音空間を形成してもいる。
「Opa-Loka」も2chで聴くよりドラマーというか打楽器奏者がふたりいる意義がわかりやすい。
また「Kings of Speed」は例外的にほとんどの楽器がフロントに定位しているように聴こえ、いちおうシンバルや残響をリアに回してはいるものの全体的にレイアウトも整理されておらずサウンドもモヤッとした印象を受ける。塊感があると言えなくもないけど。
おそらくはこうした楽曲ごとの印象の違いが、素材となったマルチトラック・テープからくる制約によるものなのだろう。……というところまで書いたあとでブックレット読み直したら「Spiral Galaxy 28948」と「Kings of Speed」はオリジナルのマルチトラック・テープが使用不可能だったから擬似的な処理を施してるよって表記されてました。たぶんGENTLE GIANTの『Octopus』マルチでやったのと同じような手法がとられてるのだと思う。
まとめると、KING CRIMSONやYESの場合のような音空間を期待すると多少欲求不満になる部分はあるものの全体としては十分聴き応えのある、楽しめるサラウンドに仕上がっていると思う。
全体的に狭っ苦しい2chから解き放たれたマルチならではの各楽器の分離の良さや音の太さがあって、レイアウトも流石わかってるひとがやってるだけあって場面ごとに的確で自然な空間が形成されている。
自分はほとんどこのリミックスを聴くためにサラウンド環境に手を出したようなものなんだけど、それだけの甲斐があったと8年近く経ったいまでも思います。えっもう8年前……?
オリジナル・マスター
ステレオ・リミックスで述べたバランスの悪さがそのまま出ているのが当然ながらこのオリジナル・マスターで、一部ミキシング由来と思われる歪みも確認できる。
しかし中低域の滑らかさはもとより、ここまであくまで問題点として扱ってきた空間を引き裂くがごときアンバランスなシンセの高音さえも、これはこれで他に代えがたい魅力であるというのもまた確か。
これはいわば原典とも呼べる音源であり、これと比較して他の音源について述べることはできても、この音源自体に対してはなんら言葉を持たないということが言えるかも知れないし雑にそれらしいこと言ってるだけかも知れない。そういうことを言いはじめたら英初版のジョージ・ペッカムによるPORKYカットがどうこうって話にまで延焼してしまう。
LP
ジャケットはインナーを含めオリジナルを可能な限り再現しており、レーベルもなんとなく元の雰囲気を残してるようなデザインになっていてこだわりを感じる。ただしインナーもレーベルも「Kings of Speed」のクレジットがなぜかブロックひとりになってるけど。
発売前のアナウンスによるとオリジナルのカッティング・マスターを元に制作されているということだが、ボックスには"Mastered from the original stereo master tapes"と表記されている。ふつうに考えていわゆるマスターテープとカッティング・マスターは別物のはずなんだけど、詳しいことはよくわからない。
盤はかなりカッティング・レベルが低くて音が小さい。アナログにおいては盤に刻まれた音が小さいということは相対的にサーフェスノイズが大きいということでもあり、自分みたいな低価格帯のオーディオでなんとか再生環境を維持しているタイプにはけっこうツラいところ。
より静音性の高い高級オーディオならともかく、ちょっと自分の環境では評価しづらいというのが正直な感想です。

マトリクスは機械打ちで、おそらくチェコのGZ Media製。
ボーナストラック
CD1-11「Motorhead」
シングル「Kings of Speed」B面曲。レミー単独作で、彼のごついベースがぐいぐいと牽引しハウスのヴァイオリンがうねる名曲。そういや『ファイブスター物語』がそれまでの「モーターヘッド」と「マシンメサイア」から「ゴティックメード」にがらっと模様替え(という表現が適切なのかわからんけど)したのもちょうどこのリイシューとおなじ2013年だった。
"Motorhead"はスピード・フリークを指すスラングで、まさにこの薬物によってHAWKWINDを追い出されたレミーは自らのグループにこの名を冠することに。
このトラックはレミーとHAWKWIND双方にとっての代表曲のひとつだが、残念ながらBen WisemanによるリマスターのみでSteven Wilsonのリミックスは作成されなかった。マルチトラック・テープの状態やレコーディング工程等の問題でリミックス出来なかった(あるいはしたところで弄ったり改善したりする余地がなかった)可能性もおおいにあるけど。
CD1-12~16の未発表音源は1975年3月のRockfield Studiosで収録されたアウトテイクやデモ。
「Soldiers At The Edge Of Time (Michael Moorcock Version)」
「On The Road」
「The Wizard Blew His Horn (Nik Turner Version)」
「Spiral Galaxy 28948 (Demo)」
「Soldiers At The Edge Of Time (Nik Turner Version」
CD1-17「Motorhead (Dave Brock Vocal Version)」
1981年に Flicknife レーベルからシングルとしてリリースされたバージョン。
オリジナルの「Motorhead」にはレコーディング当日にレミーが現れず急遽デイヴ・ブロックが歌い、その後レミーがヴォーカルを録り直してリリースされたという経緯がある。
これはヴォーカルをその際に残されたブロックのものに差し替え、その他ちょこちょことオーバーダブを加えてでっち上げられたもので、ぶっちゃけ『Ace of Spades』以降のノリにノッてるMOTÖRHEAD人気に便乗したと言われても仕方のないリリース。
聴いた感じリミックスというより本当にオーバーダブって印象なので、元々オリジナルからして4トラック程度のベーストラック+リード・ヴォーカルその他みたいな少ないトラック数しか使ってなくて、だからこそSteven Wilsonもリミックスしようがなかたっんじゃないだろうか。
CD1-18「Kings of Speed (Instrumental Version)」
アルバム・バージョンからヴォーカルや一部楽器を省いた音源というか、それらを加える前の状態のもの。
1981年にFlicknifeレーベルの第一弾としてリリースされたHAWKWIND ZOOのEPが初出で、以降様々なコンピに収録されている。またその際にライブ・バージョンと銘打たれており、それが「Silver Machine」のようにライブでの演奏をマルチトラック録音したことを指しているのか、スタジオで一発録りしたことを指しているのか不明だったのだが、今回の「Recorded at Olympic Studios, Barnes in January 1975」というクレジットを見る限りスタジオ一発録りの方を指すものだったと思われる。このトラックにヴォーカルやヴァイオリン、キーボードを加えてアルバム・バージョンを完成させたのだろう。ちな今回のリイシューでけっこう音質が向上している。
Steven Wilsonのサラウンド・リミックスでは1975年1月にOlympic Studiosで制作された
「Spiral Galaxy 28948」と「Kings of Speed」はマルチトラック・テープが使用不可能だったそうなので、おそらく「Motorhead」含めてだいたい似たような、ベーストラックを一発録りして残りをオーバーダブするような作り方をしていて、それゆえにアルバム本編に収録する必要がある前2曲はともかく「Motorhead」まではリミックスする意味がなかったということなんじゃないかと。
加えてサウンド的に「Spiral Galaxy 28948」は疑似であってもサラウンドでそれなりの効果を見込めるだろうけど、「Kings of Speed」と「Motorhead」は楽器単位でバラせるならまだしもベーストラックがまとまってる状態で擬似的にサラウンドにしたところで音響的にも効果は薄いだろうし。
CD2-11「Motorhead (Instrumental Demo)」
前曲「Kings of Speed」のInstrumental Versionとおなじような状態のトラックだけど、1975年3月Rockfield Studiosの収録とクレジットされている。
ふつうに考えて1月にOlympic Studiosでスタジオ・バージョンを収録し終えたあとでこういったデモを録音する必要があったとは思えないんだけど、どうなんでしょう。
CD2-12「Dawn」
こちらも1975年3月Rockfield Studiosの収録とクレジットされている、これまで未発表だったトラック。前作の「The Psychedelic Warlords (Disappear in Smoke)」に通じる雰囲気があるジャムセッションで、ギターのサウンドが「Opa-Loka」っぽい。
CD2-13「Watchfield Festival Jam」
これはトラック名からもわかる通り、同フェスにおけるライブ録音。
ウォッチフィールド・フェスティバルは1975年8月23日、レディング・フェスティバル(HAWKWINDがヘッドライナーを務めた)の翌日に開かれたフリーフェスティバルだった。
前日のレディングはステイシア最後のステージでありこの後バンドに復帰するロバート・カルバートがゲスト参加するというこの時期の集大成的なステージだったが、こちらは一転デイヴ、ニック、アランそしてレミーの後釜として加わった元PINK FAIRIESのポール・ルドルフという最低限の編成で、即興中心の演奏を繰り広げている。
HAWKWINDのジャムでは定番の「You Shouldn't Do That」を骨格とした演奏で、録音状態は良くないがごりごりとした勢いがありなかなか楽しい。最後「Brainstorm」に入るところでフェードアウトするのが残念。
この音源の初出はSamuraiレーベルから3枚に分けてリリースされた『Anthology』シリーズのVolume IIだった。このシリーズはなんかレーベルのオーナーがバンド側にロイヤリティまったく支払わなかったとか、勝手に音源の権利を売却しちゃったとか、その結果バンド側と無関係なコンピが乱造されちゃったとかいろいろ曰くつきだったりするので、このリイシューでやっと収まるべきところに収まったと言えるんじゃないかと。
CD2-14「Circles」
CD2-15「I Am the Eye」
これら2曲もウォッチフィールド・フェスティバルにおける即興演奏で、録音状態も同じようなもの。
どちらも80年代前半にカセットテープのみの通信販売でリリースされた『Weird Tapes』シリーズの第3巻に収録されていた(後にCD化もされている)。なおオリジナルでは「I Am the Eye」の後に「Slap It On the Table」と題された短いお遊びトラックが入っていたが、本来関係のないトラックだからかここでは省かれている。
また「Circles」は後にアルバム『Levitation』に収録される「The Fifth Second of Forever」の土台になったと思われる。
最後に
気付いてるひとは気付いてると思うんだけど、ぶっちゃけ収録音源のうちSuper Deluxe Boxset Limited Editionでなければ聴けないのはLPだけなので、音源をひととおり押さえるにはThree Disc Expanded Editionを買っておけばよかったりします。
個人的には普段どんな気になるものでも予約どころか発売日に買うことすらしない自分が予約したぐらい待ちに待ったタイトルだったので、わりとその場のノリでボックス買っちゃったけどまあ満足してます。ポスターとかポストカードとかチケットのレプリカも付いてるし、ブックレットは内容こそ同じだけど大判になってて豪華だしなにより文字が大きいので老眼にもありがたいのです。まあ自分16歳黒髪ロングJKですが
ただ以前使っていたBDプレイヤーではなぜかこのDVDだけメニュー画面で操作を受け付けず、BDプレイヤー買い換えてリミックスのハイレゾとフラット・トランスファーが聴けるようになり、それからしばらくしてやっとAVアンプ導入してサラウンド環境も構築して5.1chミックスが聴けるようになりと、わりと紆余曲折あったというかむしろこの作品のためにリスニング環境を整えていった面があったとかなかったとか。
Amazon | WARRIOR ON THE EDGE OF TIME | HAWKWIND | ヘヴィーメタル | 音楽
Standard Edition。CD1枚でボーナストラックは「Motorhead」のみ。
なんか埋め込みできねえなあと思ったらアダルト商品扱いになってた。またかよ
Three Disc Expanded Edition。リマスターCDとリミックスCDに加えてステレオおよびサラウンド・リミックスとフラット・トランスファー収録のDVDが付いた3枚組。前述したとおりここで紹介した音源はLP以外すべて入ってる
Surf City 7" / JAN & DEAN (1963)

1963年5月17日リリース。ブライアン・ウィルソンに少なからぬ影響を与えたポップ・デュオ、JAN & DEANの全米No.1シングル。
有名な話だがこの楽曲にはそのブライアン・ウィルソンが関わっている。
あるときブライアンが「Surfin' U.S.A.」をピアノで披露しているのを聴いて気に入ったジャンとディーンはぜひ自分たちのシングルにと頼み込んだもののこれはTHE BEACH BOYS用だからと断られ、代わりにいくつかの素材を提供された。それをもとに2人で完成させたのがこの「Surf City」であり、結果的に大ヒットした「Surfin' U.S.A.」をさらに凌ぐヒットを記録したということらしい。
録音は1963年の3月20日にビル・パットナムの United Western Recorders でジャンのプロデュースのもと行われ、この時代のJAN & DEANの常連であるハル・ブレイン、アール・パーマー、グレン・キャンベル、ビル・ピットマン、ビリー・ストレンジ、レイ・ポールマンという後にレッキングクルーと総称されるミュージシャンたちが参加している。またブライアン・ウィルソン自身も非公式に参加してるとか(いかにもそれらしいヴォーカルが聞こえる)。
これ以前にもそういう機会があったりしたのかもしれないが、ジャン・ベリーのスタジオでの仕事ぶりがブライアン・ウィルソンにとって大きな刺激となり、後のTHE BEACH BOYSの作品群に影響を与えたというのはよく言われることですね。
この楽曲の、そして当時のサーフ・カルチャーのキャッチフレーズである "Two girls for every boy" は、二度にわたる世界大戦と朝鮮戦争そしてベトナムという状況下で出生率を高めるために一夫多妻制を導入しようとかそういう話ではもちろんなく、たんに「両手に花」というたわいのない男の子の夢的なやつです。
当時のハリウッド製ポップスでよくある先駆的楽曲のパロディが盛り込まれたB面曲。こちらもブライアン・ウィルソンが関わっているのに加えて、JAN & DEANと交友の深いソングライターで「It Never Rains In Southern California」(邦題「カリフォルニアの青い空」)のプロデュースでも知られるドン・アルトフェルドのクレジットがある。
アルバム・バージョンと違ってイントロの台詞がカットされ、最後がフェードアウトになっている。
多分「Surf City」と同じような時期に同じようなスタジオで同じような面子(こっちはピアノがいるけど)で制作されていると思われる、ハル・ブレインのドラムを聴いてるとうれしくなってくる楽曲。

米Liberty、55580。どうやら西海岸プレスっぽい。
http://www.45cat.com/record/55580
「Surf City」の大ヒットにあやかったオリジナル・アルバム。
「She's My Summer Girl」はこちらに収録。
YouTubeで見つけた当時のPV的なもの。これを見ればジャンとディーンがどういった「キャラクター」だったか端的に理解できます。
コメント欄の詳しい人によると1963年にTVシリーズのデモとして制作された30分程度のフィルムからの抜粋で、このシリーズは結局実現しなかったらしい。
同時期にウィリアム・アッシャー監督でAIP制作の映画『ビーチ・パーティ/やめないで、もっと!』(なんやこの邦題)というヒット作もあるし、そういうやつだったんじゃないかと。
Live in Munich 1977 / RAINBOW (2005)

2005年から翌年にかけてリリースされたイギリスのハードロック・バンドRAINBOWのライブ映像。
1977年10月20日ミュンヘンのOlympiahalleでの公演をおそらくフル収録しており、もともとはドイツのテレビ番組Rockpalast用に撮影され長らくブートレグの定番だったらしい。
ロニー・ジェイムス・ディオとコージー・パウエルを擁する時期のパワフルなパフォーマンスを十分な画質と音質でたっぷり楽しめるありがたいソフトで、『On Stage』はもちろん『Live In Germany 1976』にも収録されなかったコージー・パウエルの「1812年」を含むドラムソロがついに、しかも映像で公式リリースされたことも話題になった(少なくとも俺の中では)。
- リッチー・ブラックモア Ritchie Blackmore:Guitar, Moog Taurus
- ロニー・ジェイムス・ディオ Ronnie James Dio:Lead Vocals
- デイヴィッド・ ストーン David Stone:Keyboards
- ボブ・ディズリー Bob Daisley:Bass, Backing Vocals
- コージー・パウエル Cozy Powell:Drums, Percussion
このときRAINBOWは1976年の日本ツアーを中心に収録したライブ・アルバム『On Stage』リリースに伴うツアーの最中で、次のスタジオ・アルバムとなる『Long Live Rock 'n' Roll』の制作途中でもあった。
メンバーは『On Stage』からベースとキーボードがそれぞれボブ・ディズリーとデイヴィッド・ ストーンに交代している。
セットリストは基本的に『On Stage』の頃と共通で「Stargazer」が新曲「Long Live Rock 'n' Roll」に入れ替わったくらいだろうか。
どの曲もリッチー・ブラックモアが他のメンバーに指示を飛ばし全体をコントロールしつつ自身はわりと自由に崩したバッキングを弾きソロも各曲の冒頭間奏後奏とあらゆる場面でたっぷりと披露していてスタジオ・アルバムとくらべてやたら演奏時間が長い。はじめて聴いたときはギターソロが多いし長いしえらいこっちゃと思った『On Stage』もこうしてみるとレコード向けにずいぶんかっちり再構成してたんだということがわかる。
そんなわけなのでロニー・ジェイムス・ディオの力強く安定した歌唱もコージー・パウエルや他のメンバーのプレイも魅力的だけども、結局なんもかんもリッチー次第というくらい音楽的に彼の占める要素が大きい。
とはいえコージー・パウエルは重要で、RAINBOWのライブにおける全盛期はコージーがいた時代と言われるのも納得のプレイ。
彼のドラムはたしかに派手だけどあくまで引き立て役に徹していて、引くところはわりとすぱっと引くうえでの押し出し方のバリエーションが豊富でともすれば(しなくても)延々とギターの音が垂れ流されるだけになりかねない演奏にメリハリをつけている。
リッチーのギターソロがこれほどドラマティックに決まるのはコージー(とキーボーディスト)あってのことで、後任のボビー・ロンディネリにしろチャック・バーギにしろきっちり作られた楽曲をきっちり演奏するという点に関してはコージーより適任だっただろうがライブでここまでの、言ってしまえば「面倒見の良さ」を発揮することはなかったように思う。
ボブ・ディズリーはそのコージーの補助としてバックコーラス含めそつなくこなしている印象で、そもそもRAINBOWがベーシストが魅力を発揮できるバンドじゃないという前提のもとで十分いい仕事をしている。ジミー・ベインより音の粒立ちがよくて細かいパッセージをバリバリ演ってるように聞こえるのはミキシングの問題もあるかなぁ。
元SYMPHONIC SLAMというだけあってか歴代キーボーディストのなかでも幅広い機材を揃えたデイヴィッド・ ストーンは雰囲気作りが主な仕事で、よくよく聞くとジョン・ロードに負けないけっこうエグめに歪んだハモンドを弾いてたりもするのだがミキシング・バランスそのものがギターの補強的な使われ方なので目立たず、ところどころのソロもあまりパッとしない。
『On Stage』でのトニー・カレイがわりとリッチーの向こうを張るようなプレイでミキシング自体そういうレイアウトだったことから考えると、彼の脱退をもってこのバンドにおけるキーボードの立ち位置自体が変わり、本格的にリッチーのワンマン化がはじまったとも言えるのかも。
リッチーはおそらくこの1977年ツアーからMoog Taurusを導入している(1976年ツアーの音源と比較した印象)。よくギタークラッシュの際に迫力を出すためと言われているし実際そういう面もあるのだろうが、この映像で観るとそれに限らずライブの前半からちょくちょくギターソロの補助的に使用しているのがわかる。
またデイヴィッド・ ストーンもTaurusっぽい重低音を出してるんだけど足元を確認できるカットがなく、まさかリッチーがキーボードの伴奏なんかするわけねえよなぁと思っていたところ後述するPVでストーンの足元にもTaurusがあることが確認できた。
ギタークラッシュに関しては1976年のライブではバンドが演奏を続けるなかぶっ壊してたけど、ここでは他のメンバーがステージを去ってから「じゃあこれからギター壊しますんで」みたいな感じで事に及んでいる。かなり最前列の観客に近いところでがっしゃんがっしゃんやってて最初は興奮して手を伸ばしてた客が途中から怖がってたり。もし自分がこの場でうっかり最前列になってたら前はリッチー後ろは押し寄せてくる観客に挟まれて泣く。
手持ちのDVD2枚組国内盤は2005年12月にvapから海外に先駆けてリリースされたもので、ピカピカの紙ケース(なんとも言い難いデザイン)入りのツヤツヤした真っ黒のデジパック(すごく指紋が目立つ)におまけでギターピックが付属している(いらない)。
海外では2006年に入ってからまったく違うデザインのパッケージでEagle Visionなどからリリースされ、こちらは国内盤と同じ内容に加えて評論家によるコメンタリー付きスライドショーも収録されてDVD1枚に収まっているっぽい。はっ?
ついでにUS盤はリージョン1と4でEU盤はリージョンフリーだけどPALだったはず。
国内盤DVD収録の本編音声は以下の3種類。
ミックスを手掛けたのは本編最後のクレジットによるとstevescanlon.netというところで、名前からしてSteve Scanlonさんご本人かその息のかかった人物の手による仕事だと思われる。
ミックスはステレオもサラウンドも『On Stage』とは違い各楽器がほとんど中央に寄せられたレイアウト。といってもヴォーカルとギター以外の楽器はちょっと脇にずらされてるような感じがして全体的な位置関係というかレイアウトのバランス(あるいは音像とでも言えばいいだろうか)が微妙なんだけど、それなりにクリアで各パートを聞き分けやすくタウラスの低音もわりと出ている。
サラウンドではリアに歓声が増えるくらいで演奏自体はステレオとレイアウト的にそんなに違いはなく、ぶっちゃけステレオを元にした擬似的なものだろうと思うんだけどなんかステレオより全体的なダイナミックレンジが広くなってギターの音の粒立ちがよくベースやドラムそしてタウラスの音が太くなってるような気がする。
サラウンドと比べるとステレオはどうしても低音が細くて全体的に軽い印象で、おそらく同じソースからのCD音源とこのDVDのDolby Digital 2.0chをざっと比較してもたいした違いはなかったし、さしあたってこのライブに関してはDTS 5.0chがベストかなと思わなくもない。正直1977年当時放送された際の音声がどんな感じでこのDVDに際してどの程度いじられてるのかよくわからないので無駄な警戒心が抜けないままになっちゃてるとこあります。あと自分はやっぱり『On Stage』のギターとキーボードが左右のチャンネルにくっきり分かれて配置されたレイアウトのが好きだなぁとも。
画質は当時の16mmフィルム撮影ということを踏まえれば十分鑑賞に耐えうるもので、カメラもそれなりの台数が用意されていてわりと見たい場面で見たい部分をしっかり見せてくれる。
ステージにかかるコンピューター制御の虹、リッチーが一瞬ギターのチューニングを直そうとしてすぐあきらめる様子、ロニーが間違えてベース側のコーラス用マイクで歌いはじめて音が入らない場面などがばっちり確認できる。
そういえば以前グラハム・ボネットがRAINBOW時代にライブで前座を務めたBLUE ÖYSTER CULTについてなにかのインタビューで「あいつらは保守的だから俺達とは合わなかった」みたいなこと言ってたのを読んだけど、ライブにいち早くレーザーショーを導入してみたものの様々な問題から継続できなかったBLUE ÖYSTER CULTからすれば大掛かりな虹のセットに予算を注ぎ込んでともすれば赤字を出しつつツアーするRAINBOWはなんやこいつらって感じもあったんじゃないだろうか(妄想)。
特典ディスクの内容はアルバム『Long Live Rock 'n' Roll』からのPV3つとコリン・ハートそしてボブ・ディズリーへのインタビューにあとフォトギャラリー。
「Long Live Rock 'n' Roll」「L.A. Connection」「Gates of Babylon」という3曲のPVは『Long Live Rock 'n' Roll』リリース後のアメリカ・ツアーに先立ってテレビ番組Don Kirshner’s Rock Concertで放送するために制作されたもの。
音声はモノラルで3曲とも楽器は当て振りだけどロニーのヴォーカルだけこの映像独自のものになっていて、この後『Long Live Rock 'n' Roll』のデラックス・エディションにアウトテイク含めたすべての音源が収録された。
多少演出があるとはいえスタジオに機材置いてふつうに演奏してるだけのシンプルな映像で、個人的見どころは「Gates of Babylon」でリッチーのギターソロのあとカメラがロニーに切り替わるとリッチーを撮影してるカメラマンのひとがばっちり画面に入ってしまいカメラがおもむろに向きを変える場面。
あとステージでの映像より画面が明るいおかげでデイヴィッド・ ストーンの足元に設置されてるMoog Taurusが確認できてすっきりした。
コリン・ハート(長年DEEP PURPLEやRAINBOWのツアーマネージャーを務めた人物)とボブ・ディズリーのインタビューはどちらもそれぞれに興味深い内容だが、そこで共通して語られるのがこのDVD本編のミュンヘン公演の2, 3日前、オーストリアでの公演の直後にリッチーが逮捕された事件について。
2人が語るいきさつは微妙に異なっているものの、リッチーがなにかしらの理由で劇場支配人を蹴飛ばして警察を呼ばれ機材ケースに隠れて会場を脱出しようとしたものの警察犬に見つかったというところは共通している。
警察犬といえばHAWKWIND(ボブ・ディズリーの話にちょろっと出てくるヒュー・ロイド・ラントンがいたバンドでもある)もお薬関係で警察にマークされライブ中に踏み込まれたことがあり、こちらはとっさにシンセサイザーで人間の可聴域を超えた音を大音量で流して警察犬を暴れさせて事なきを得たとか。
そういえば書き忘れてたけど本編のMCにもインタビューにも日本語字幕ついてます。
2013年のリイシュー盤には2006年盤の内容に加えて「Rainbow Over Texas ’76」と題された1976年アメリカ・ツアーの様子を伝えるショート・フィルムが追加されていて、これ1本でロニー時代の主要な映像をだいたい押さえられるようになった。
US盤こそリージョン1だけどEU盤はNTSCのリージョンフリーっぽい。あと本編音声のうちDolby Digital 5.0chがDolby Digital 5.1chに変更されてるような雰囲気。
日本ではなぜか2012年という微妙すぎるタイミングでやっと2006年の海外盤と同じ仕様(ただしオマケ付き)でリイシューされて2013年盤はスルーされた。なんじゃそりゃ
QUEEN (1973/2011)

QUEENはおそらくTHE BEATLESと並んで世界的に有名なイギリスのグループで、1970年にロンドンで結成された。ハードロックを基調としつつ時代に合わせ様々な音楽的要素を取り入れていったグループだが、この1stアルバムの時点での音楽性はハード化したグラムロックとでも言うべきもの。
その1stアルバムとなる今作は1973年7月13日リリースで、プロデュースはバンド自身とジョン・アンソニー、そしておそらくこのバンドの音作りの立役者であろうロイ・トーマス・ベイカー。邦題は『戦慄の王女』だった。
- フレディ・マーキュリー Freddie Mercury:Vocals, Piano
- ブライアン・メイ Brian May:Guitars, Piano, Vocals
- ジョン・ディーコン Deacon John:Bass Guitar
- ロジャー・テイラー Roger Meddows-Taylor:Percussions, Vocals
70年代のQUEENを特徴付ける多重録音を駆使した独特の厚みのあるギターとコーラス、それらを最大限活用したときに華麗でときに暴力的な目くるめくアレンジといった要素はこのアルバムにおいてすでに完成されていると言っていいと思う。
反面、めいっぱいアイディアを詰め込んだのであろう結果としてクドさやとっ散らかった感じが耳につき、どの曲も凝ってるんだけどそれ故にどの曲も似たような展開になりがち、という問題も。
とはいえ初期QUEEN特有のこのむせ返るような濃厚さには独自の魅力があり、これこそ4thアルバム『A Night at the Opera』に至る過程で整理・洗練されていくその原液とも言えるんじゃないかと思う。
あとQUEENと少女漫画の関係については不勉強なんだけどなんとなく魔夜峰央的な絵柄を連想したりする。魔夜峰央でQUEENだとむしろ「フラッシュのテーマ」だろうけど
QUEENは1971年、ホルボーンからウェンブリーに移設したばかりの De Lane Lea Studios で1stアルバムの素材となるデモ・テープのレコーディングを開始。これをプロデュースしていたジョン・アンソニーの紹介で翌72年にノーマンとバリーのシェフィールド兄弟に招かれ、彼らが設立した名スタジオ Trident Studios で夜の空き時間を使って本格的なアルバム制作にとりかかった。
エンジニアリングはジョン・アンソニーやロイ・トーマス・ベイカーに加えてデヴィッド ・ヘンチェル、マイク・ストーンといった当時のTrident StudiosのスタッフあるいはQUEEN自身がその時々に応じて担当していたようだ。
つまりこのアルバムは、デヴィッド・ボウイやT. REX、エルトン・ジョンといった面々の出入りする言うなれば当時のブリティッシュ・ロックの最前線であるTrident Studiosで、そのスタッフたちも交えてじっくり時間をかけて制作されたということになる。
だからこそロイ・トーマス・ベイカーのトレードマークである執拗な多重録音やデッドで厚みのあるもこもこドラムなどをふんだんに盛り込みつつも、それらがたんなるプロデューサー主導のレコーディングで終わらずQUEENというバンドの音楽性として昇華されているのだろう。
なおアルバムは途中フレディがラリー・ルレックス名義でシングルを作ったりしつつ1972年11月頃に完成したものの、レーベル探しが難航し英EMIからリリースされたのは翌73年も半ばになってからであった。
ノーマン・シェフィールドはこれ以降バンドのマネージメントに敏腕を振るい躍進のきっかけを作るとともに、フレディ・マーキュリーが彼に捧げたといわれる「Death On Two Legs」等創作の原動力にもなったりならなかったり。
- Keep Yourself Alive
アルバムに先行してリリースされたデビュー・シングルで、邦題は「炎のロックン・ロール」。カウベルが足りない
自分がQUEENを聴きはじめた頃は手元にたいした資料がなく今ほどインターネットも一般的じゃなかったもんで、しばらく「炎のロックン・ロール」と「誘惑のロックン・ロール」(「Now I'm Here」の邦題)がどの曲を指すのかわからず、とりあえずどっちかは「Modern Times Rock 'n' Roll」の邦題だろうと予測してたら全然違ったりなどした思い出。
たぶんQUEENでもっともグラムっぽいキャッチーさを備えたトラック。
- Doing All Right
イントロのピアノはだいぶエコーがかけられてるけどそれでも「Lady Stardust」や「Tiny Dancer」と同じあのベヒシュタインだということを思い出させる。
この時期ならではなフレディ・マーキュリーの瑞々しい高音が楽しめるゆったりとした前半から曲調が変わってそこに歪んだギターが入ってきて…というやつ。
SMILE(QUEENの前身となったグループ)時代からある楽曲で、当時のヴォーカリスト、ティム・スタッフェルとブライアン・メイの共作。
- Great King Rat
- My Fairy King
2曲とも初期QUEENを象徴する執拗かつ過剰な楽曲で、左右のチャンネルを目まぐるしく行き交うギターとコーラス、緩急の激しいコテコテとも言える曲展開とそれに合わせて細かく変化するエコーなど、残響に至るまで作り込んだこの思いっきり「やらかしちゃってる」感は他に代えがたい。こういった一面を指してプログレ的と言われたりもする。
凝った音作りの代償として音質的にはかなり苦しい。
原液感ある。
- Liar
当時のライブでハイライトとして演奏され後年のツアーでも取り上げられる機会の多かったこの時期の代表曲で、ハードロック色が強いトラック。
アメリカでのみ3分ちょいに編集されシングル・リリースされた。
- The Night Comes Down
不穏なイントロから一転してフレディが繊細な歌唱を聴かせる楽曲で、このアルバム内では比較的シンプルな音作り。あとカウベル。こんなシンプルなら全体的にもっとクリアな音になりそうなものだけどそこはエコーなどでばっちりお化粧を施されてちゃんと(?)もやもやした音になってる。
このトラックのみDe Lane Lea Studiosでのテイクが採用されている。
- Modern Times Rock 'n' Roll
アルバム中唯一ロジャー・テイラーの作曲とリード・ヴォーカル。
小品ではあるけどギターのバッキングがけっこう美味しい、のちの「Stone Cold Crazy」や「Sheer Heart Attack」に通じるハードな曲調。
- Son and Daughter
QUEENにはわりとめずらしいブルース・ベースのヘヴィ・ロック。
- Jesus
リズムとコーラスが特徴的で「他とはちょっと違った調子の曲だな〜」と聴いてると案の定盛り上がる。正直そんな長々と盛り上がらなくてもとか思ってたんだけど、De Lane Lea Studiosでのデモが公式に聴けるようになったことでこれでも当初よりだいぶ短くなってることが判明した。
- Seven Seas Of Rhye...
アルバムの最後を飾るインストの小品。この後ヴォーカルが付いてシングル・カットされたり2ndアルバムに収録されたりするもんだからなんとなくYMOの「以心電信」を連想するように。

このアルバムのジャケットは英EMI盤と米Elektra盤で異なり、米盤の方は英盤ジャケをトリミングしたものになっている。
日本のWarner-Pioneer盤は米Elektra配給で、ジャケットも米盤に倣ったもの。正直ジャケットに関しては英盤のが魅力的なような。
裏ジャケは英盤と米盤でロゴやクレジットのレイアウトが異なるものの基本的なデザインは共通で、おなじみ「No Synthesizer」表記や18年後にまさかの再登場を果たすことになる謎のペンギン男の写真等がある。

日Elektra/Warner-Pioneer、P-8427E。
音質はまあこんなもんだと思う。正直70年代のQUEENは凝った音作りの代償としてマスター・テープの段階からけっこうな音質劣化があるように思えるんだけど、英初期盤とかどんなもんなんだろ。
2011年にはQUEENの全アルバムが「Queen 40th Anniversary」シリーズとしてボーナス・ディスク付きの決定版とも言える仕様であらためてリイシューされた。
このシリーズのリマスターは有名なエンジニアの Bob Ludwig が手掛けており、このアルバムに関して言うとクリアながら音圧重視でダイナミックレンジが狭い仕上がりとなっている。ダメでは
Album details - Dynamic Range Database
本来比較対象にしなきゃいけない古いCDを手放してしまって幾年月なのではっきりしたことは言えないが、おそらくアナログ・マスターから丁寧にデジタル化やノイズリダクション(これも手放しで歓迎できるわけじゃないけど)を行ってはいて、でもついでに音圧も上げちゃってるので台無しは言い過ぎだとしてもちょっちキツいな〜という印象。カーステでなるべく音量調節したくないときとか小さめの音で流しておきたいときにはいいかも知れない。
日本限定でSHM-SACDがリリースされたりもしたけど元にしてるのはこのリマスターだそうなので、もちろん実際聴いてみないとわからないとはいえ正直期待できそうにない。
それはそれとしてボーナス・ディスクの内容は上記した1971年De Lane Lea Studiosでのデモ音源5つとアルバムのアウトテイク「Mad the Swine」となっていて、こちらはどれも興味深い内容。
リマスタリングもボブではなく Adam Ayan が手掛けていて案外悪くない。
De Lane Lea Studiosでのデモはおそらく盤起こしだが音質は十分良好で、しかもデモと言ってもアレンジどころかミキシングまで含めかなり完成品に近い段階まで仕上がっている。
この時点ですでにQUEEN側のレコーディングに対するイメージがある程度固まっていて、だからこそ実際に出来上がったアルバムがああいったものになったのだろうことを伺わせる。
ていうかロイ・トーマス・ベイカーが噛んでない分ドラムの音が残響を含むクリアなサウンドになってるし多重録音や執拗なエコー操作で各楽器のディテールが霞んだり全体がぼやけたりしてないので、この方向性でも十分いいアルバムに仕上がってた疑惑がある。ただまあその場合あくまで「この時代の音」の範疇に収まった作品止まりで、そこを突き抜けたものにはなっていなかったかも知れないが。
「Mad the Swine」はアウトテイクだけど軽快でなかなか良いトラック。
1つ1つが作り込まれた結果ある種の箱庭感というかぼんやりと閉じた感じのあるアルバム本編のトラックに対し、これはもうちょっと緩くて開放的。残響感のあるドラムや過剰なエコーがない音作りからして完成したアルバム本編よりDe Lane Lea Studiosでの音作りに近くて、だからこそ他との兼ね合いで外されたんじゃないかと思わずにいられない。
あとこのトラックはなぜか1991年にシングル「Headlong」のカップリングとして蔵出しされたのが初出なはず。
サブスクだとなんか追加で3曲のライブ・クリップも観られたりするっぽい。

![Hawkwind Live 1984-1995 [DVD] [Import] Hawkwind Live 1984-1995 [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lN+5J692L.jpg)



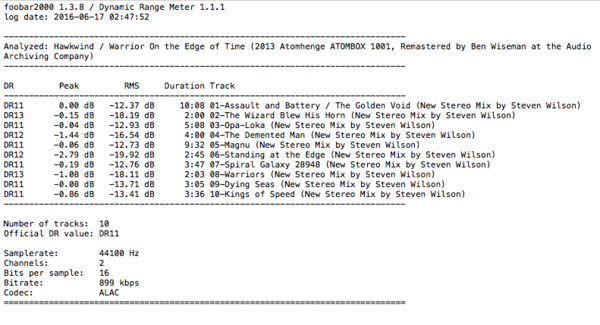




![リッチー・ブラックモアズ・レインボー・ライブ・イン・ミュンヘン 1977 [DVD] リッチー・ブラックモアズ・レインボー・ライブ・イン・ミュンヘン 1977 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/31WRD991AZL._SL500_.jpg)